2009年04月24日
カワセミ勉強「宍道湖グリーンパーク」
今回はカワセミの人工営巣例として、こちらをチェック。
芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、
海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。
★宍道湖グリーンパーク
サイトに載っている写真が小さいのですが、
いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。
現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、
さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、
Telでインタビューしました。
・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。
・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。
・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。
・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。
・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。
専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、
基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。
また、意外とこじんまりしていますが、
カワセミの広く固い縄張りを考えれば、
(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)
このくらいで良いのかも。
# うちも、これなら作れる?
そして、今回のインタビューで、
一番勉強になったのが、この2点のつながり。
・ なんで普通に土の壁にしないのか、と
・ 埋め戻しという運用。
何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、
ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、
これだと連続運用に支障が出るらしいです。
何でかというと。
カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、
そこで1シーズンに1~3回程度、
産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、
次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。
そこで最後の巣立ちが終わったら、
巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。
フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。
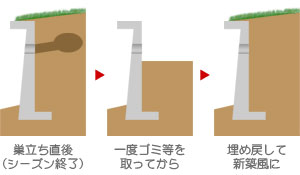
その際、コンクリの壁が建っていれば、
上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、
オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。
まー、言われてみればその通りなんですが、
やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。
ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。
宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。
こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、
初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功
しかし!
上手くいったと思っていたら、
その翌年から営巣しなくなってしまった
そこで埋め戻しをしてみたところ─────
その次のシーズンに、再び営巣成功
これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、
昨年まで3年連続で営巣継続中
今年も既に抱卵しているようなので、
このまま無事に行けば、
4年連続の営巣成功まちがいなしです

埋め戻しスゴイ!
港区セミプロも参考にしたいと思います。
宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!
芝浦・港南の運河と、規模は全く違うものの、
海近の汽水域で、富栄養という共通点があります。
★宍道湖グリーンパーク
サイトに載っている写真が小さいのですが、
いわゆるカワセミブロック系の人工営巣地です。
現地へ行ってみたいのはヤマヤマですが、
さすがに東京→島根では、気楽に見学というわけにもいかず、
Telでインタビューしました。
・ 営巣壁は、普通の護岸用(?)PCに直径5cmの穴を開けたもの。
・ 2m幅のPC1枚あたり穴を2コ。それを3つ連結したので穴は都合6コ。
・ 露出部の高さは約1.5mで、地面から1mくらいのところに巣穴。
・ 天頂部に板を張り出させて、蛇避けに。
・ 約2mの草地をはさみ、園内の人工池に向けて建っている。
専用のカワセミブロックを使っているわけではないそうですが、
基本的な考え方や、構造はほぼ同じようです。
また、意外とこじんまりしていますが、
カワセミの広く固い縄張りを考えれば、
(=どうせ1カップルしか使えないわけだから)
このくらいで良いのかも。
# うちも、これなら作れる?

そして、今回のインタビューで、
一番勉強になったのが、この2点のつながり。
・ なんで普通に土の壁にしないのか、と
・ 埋め戻しという運用。
何もわざわざコンクリの壁に穴なんてことをせず、
ただモコっと土を削れば良いのではないかと思ったのですが、
これだと連続運用に支障が出るらしいです。
何でかというと。
カワセミは繁殖前に自分で巣穴を掘り、
そこで1シーズンに1~3回程度、
産卵→巣立ち→産卵→と繰り返すらしいのですが、
次の年に同じ穴を使うのは好きじゃないようです。
そこで最後の巣立ちが終わったら、
巣穴を埋め戻してあげるという「運用」が必要。
フレッシュな新築物件にしてやらないとダメなんですね。
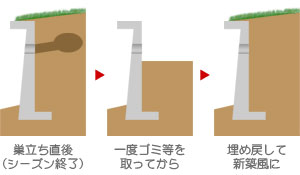
その際、コンクリの壁が建っていれば、
上から掘って、もう一回埋めてあげるのも可能ですが、
オール土の壁だと、積もうとしても崩れてしまう、と。
まー、言われてみればその通りなんですが、
やはり実際に使っている方の経験値はスゴイ。
ちなみに、この「埋め戻し」という運用方法。
宍道湖グリーンパークで、絶大な効果を上げているそうです。
こちらでは、カワセミ用営巣地を作って、
初めて迎えたそのシーズンに、いきなり営巣成功

しかし!
上手くいったと思っていたら、
その翌年から営巣しなくなってしまった

そこで埋め戻しをしてみたところ─────
その次のシーズンに、再び営巣成功

これ以降、毎回埋め戻しをするようにして、
昨年まで3年連続で営巣継続中

今年も既に抱卵しているようなので、
このまま無事に行けば、
4年連続の営巣成功まちがいなしです


埋め戻しスゴイ!
港区セミプロも参考にしたいと思います。
宍道湖グリーンパークさま、ありがとうございました!
【オカモト】
続きを読むPosted by カルガモプロジェクト at
19:56
│Comments(0)
2009年04月23日
カワセミも呼びたい!カワセミ・プロジェクト
「カルガモは上手く進んでいる感じ」
「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」
これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、
カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。
(※予算は付いていませんので、研究段階です)
そもそも、
「都市部でカワセミ?」
と思われるかもしれませんが、
カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、
港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────
なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。
その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。
# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、
# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。
この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、
・ 東京が一時期よりキレイになったこと。
・ カワセミ自身がたくましくなったこと。
が、理由ではないかと考えられています。
もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、
「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、
専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、
方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。
さて。
初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、
周辺調査からスタートしてみます。
★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。
ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。
私自身、カルガモ研究目的で行った際に、
こちらで偶然カワセミを見かけ、
「え? こんなところにカワセミ??」と、
興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。
前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、
詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。
★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。
─カワセミは見られますか?
「見られる」
─営巣した実績は?
「詳しく観察していないので不明」
★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。
─カワセミは見られますか?
「見られる」
「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」
「採餌場所は、塩水でも問題ない」
─営巣した実績は?
「ない」
─なんで野鳥公園では営巣しないの?
「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」
「むき出しの土壁が無いと営巣しない」
なんか─────見るだけなら結構いそうですね
本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?
さて、今回のヒアリング結果を、
芝浦・港南地区にあてはめてみると、
・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。
・ やはり問題は営巣するための「土の壁」
ということのようです。
「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。
掘る式は白金の例と同様で、
『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。
(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)
積む式は、面白い情報をもらいました。
2002年、墨田区押上で─────
なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」
# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様
# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様
# 本当にありがとうございます!
これは特異な例と見られているようですが、
実績は実績として、とても参考になります。
# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。
# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ
なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。
積む式の亜種みたいなものでしょうか。
このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。
北海道=雄大な自然というイメージですが、
やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、
カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。
★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例
旭川河川事務所サイト
それにしてもカワセミは、さすがアイドル!
カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。
これはなかなか幸先が良いですよ。
ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。
セミプロは課題山積みです!
「次は水辺の宝石、カワセミを呼ぼう!」
これが、カモプロ内の趣味サークル(?)、
カワセミ・プロジェクト、略して「セミプロ」です。
(※予算は付いていませんので、研究段階です)
そもそも、
「都市部でカワセミ?」
と思われるかもしれませんが、
カモプロの本拠地である、芝浦・港南から直線でほんの2~3km、
港区白金には1988年(今から20年ほど前)に戻ってきて─────
なんと「ゴミ埋め用に掘った穴」で営巣。
その後も、割合とコンスタントに、連続営巣しています。
# この件は『帰ってきたカワセミ』矢野亮(地人書館 1996)で、
# 非常に詳しい記録を見ることが出来ます。
この例に限らず、カワセミの都心回帰は進みつつあり、
・ 東京が一時期よりキレイになったこと。
・ カワセミ自身がたくましくなったこと。
が、理由ではないかと考えられています。
もちろん、芝浦・港南地区での営巣可能性についても、
「夢物語ではなく、十分に可能性はある」と、
専門家の先生も、口を揃えてくださっていますので、
方法・場所・費用など含め、より具体的な研究を進めたいと思います。
さて。
初期段階として、カルガモ・プロジェクトの時と同様、
周辺調査からスタートしてみます。
★西のご近所【国立自然教育園】は、都会派カワセミの聖地。
ここでは出現率50%くらいの高率で、カワセミに出会えます。
私自身、カルガモ研究目的で行った際に、
こちらで偶然カワセミを見かけ、
「え? こんなところにカワセミ??」と、
興味を持ったのがセミプロへのきっかけ。
前述『帰ってきたカワセミ』の舞台でもありますので、
詳細はそちらを読んでいただくとして、ここでは省略。
★北のご近所【浜離宮恩賜庭園】に聞いてみました。
─カワセミは見られますか?
「見られる」
─営巣した実績は?
「詳しく観察していないので不明」
★南のご近所【都立東京港野鳥公園】に聞いてみました。
─カワセミは見られますか?
「見られる」
「海側の干潟で、小魚やエビなどを採食」
「採餌場所は、塩水でも問題ない」
─営巣した実績は?
「ない」
─なんで野鳥公園では営巣しないの?
「コンクリの護岸や、草に覆われた斜面しかないからと思われる」
「むき出しの土壁が無いと営巣しない」
なんか─────見るだけなら結構いそうですね

本当は気付かないうちに、頭の上を飛んでたりして?
さて、今回のヒアリング結果を、
芝浦・港南地区にあてはめてみると、
・ 餌の問題はなさそう(塩水/海生物でもOKと再確認)。
・ やはり問題は営巣するための「土の壁」
ということのようです。
「土の壁」を作るには、掘るか積むか、どちらかとなるでしょう。
掘る式は白金の例と同様で、
『帰ってきたカワセミ』には、理想形も掲載されています。
(観察小屋込みで、MAX10m×10mくらいのスペースがあると理想)
積む式は、面白い情報をもらいました。
2002年、墨田区押上で─────
なんと「建築用の砂を積んでおいたら営巣」
# 情報を教えていただいた、日本野鳥の会・安西英明様
# 快く資料を提供して下さった、著者の都市鳥研究会・川内博様
# 本当にありがとうございます!
これは特異な例と見られているようですが、
実績は実績として、とても参考になります。
# というか、ゴミ用の穴とか、建築用の砂とか...。
# 「水辺の宝石」カワセミって何なんだ

なお土壁ではなく、カワセミ用穴あきブロックでの営巣成功例もあります。
積む式の亜種みたいなものでしょうか。
このブロックでの営巣試験は、北海道の旭川で始まったようです。
北海道=雄大な自然というイメージですが、
やはり大きい河川は護岸整備が進んでいるので、
カワセミ用の「土の壁」は、なかなか無いようですね。
★カワセミの人工営巣「ブロック壁バージョン」例
旭川河川事務所サイト
それにしてもカワセミは、さすがアイドル!
カルガモのときと違って、研究情報も豊富です。
これはなかなか幸先が良いですよ。
ただ─────どこを掘るか、どこに積むか、あるいは新方式開発か。
セミプロは課題山積みです!
【オカモト】
Posted by カルガモプロジェクト at
16:02
│Comments(0)
2009年04月21日
2009年04月20日
抱卵中!

壁を取り払いリフォームした部屋の草がなぎ倒されています。
この部屋の隅を見てみると・・・

母ガモが一生懸命卵を温めていました。
卵は何日もかけて12個ほど生むそうですが、
卵の温め方を調整して、どの卵も同時に生まれるようにするのだそうです。
抱卵中のカルガモを観察できるのは極めて珍しいこと!
暖かく見守ってやりましょう!
Posted by カルガモプロジェクト at
23:28
│Comments(0)
2009年04月15日
2009年04月14日
卵発見!

カルガモのカップルが桟橋の上で日向ぼっこしていました。
もうすぐメスはオスと別れ、一人で巣を作り、卵を産むはずです。
しかし今年は、4月に入っても寒い日が続き、カルガモの巣の草の生長も遅いようで、身を隠すほどにはなっていません。
そこで、草を増やすために、荒川の河川敷まで草の採集に行ってきました。
カルガモの巣に使う草は、海水を被っているような海辺の草でなければいけません。
運河は塩分濃度が低いとはいっても、やはり通常の草では枯れてしまうからです。
ここは、荒川河口にある若洲運河沿いの川原
大潮の満潮時には海水を被ってしまう場所です。
辺りは流れ着いたゴミが散乱してます。


草はこのように土の付いた株ごと採取します。
芝浦運河に戻って、草を植える前に休息所の清掃。



草を持って巣に近づきます。

巣の中は踏み荒らされたように草がなぎ倒されています。
カルガモの仕業でしょうか?
リフォームで壁を取り払った南東の隅をみてみると・・・

おおおおぉぉ!!

卵発見!

ニワトリの卵ほどの大きさです。
数は2個

通常は何日かかけて12~15個くらい生みますから、今は出産の真っ最中なのかもしれません。
あまり長居をしていては、親鳥が巣を放棄してしまう危険があるので、写真を撮ったらすぐに退散します。
そこに、カァ~!カァ~!という鳴き声が・・・



カルガモの卵やヒナを食べてしまう恐ろしいカラスが、こっちを見ています。
ヒナが無事に生まれ、育つ事を祈りながら、みんなで観察して行きましょう。

カルガモプロジェクトではメンバーを募集しています。
一緒にカルガモの観察や、巣のお手入れ、野鳥の勉強などをしてみませんか?
連絡先
港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課 地区政策係
電話03-6400-0013
Eメール minato82@city.minato.tokyo.jp
Posted by カルガモプロジェクト at
16:54
│Comments(3)
















